「会社で思った成果が出ない・・・。」
「会社組織編成がうまくいかない・・・。」
どの会社でもこんな悩みを抱えている人はいます。
逆にこういった悩みを抱えていない会社はありません。
それは、会社の組織はパレートの法則や262の法則で成り立っているからです。
パレートの法則や262の法則は、会社の人間関係や組織の人材育成、仕事の成果など、様々なビジネスシーンで成り立っている法則です。
会社での成果や組織編成に悩んでいる方には、解決策に繋がる考え方なので、参考にしてみてください。
パレートの法則とは
パレートの法則とは、イタリアの経済学者ヴィルフレド・パレートが発見した法則です。
全体の数値の大部分は、全体を構成するうちの一部の要素が生み出しているという理論です。
例えば、会社の利益の場合、組織全体の2割の社員が大部分の利益をもたらしています。
そして、その2割の社員がいなくなっても、残り8割の中の2割がまた大部分の利益をもたらすようになるということです。
262の法則
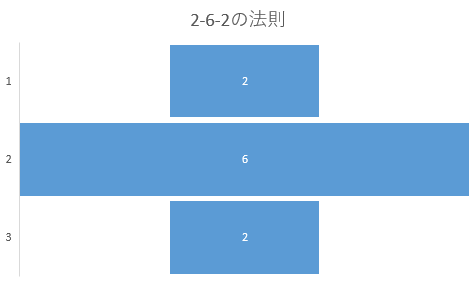
パレートの法則をもう少し細かく見ていくと8:2の構成比が2:6:2に分類できることがあります。
この2:6:2の構成比を262の法則と言います。
先ほど例にした会社組織であれば、組織全体の2割の社員が大部分の利益をもたらしていると解説しました。
262の法則だと、8割の部分を6-2に分類します。
2ー6-2の中で「会社の利益に大きく貢献してくれる2割」と「そこそこ貢献している6割」、そして「あまり貢献していない2割」となるのです。
「あまり貢献していない2割」を排除ところで、新しく「あまり貢献していない2割」は出てきます。
日常のなかで見られるパレートの法則と262の法則
私たちの日常にはパレートの法則と262の法則にあてはまることが多くあります。
会社の組織
先ほども解説しましたが、多くの会社組織でもこの法則があてはまります。
2割の社員が全体の8割の利益を作り、残りの8割の社員が後の2割の利益をつくると言われており、パレートの法則が成り立ちます。
仮に成績の悪い下位2割の社員を切っても、新たに中間の6から下の2が生まれる262の法則もあてはまります。
中間の6の社員の中には、下の2の社員より上にいることで、モチベーションを維持しているケースがあります。
こういったモチベーションの場合、下の2の社員がいなくなると、それまで6にいた自分が下の2になってしまうことで、モチベーションを一気に低下させてしまう人もいたりします。
こうして新たな下の2が生まれます。
もちろん、危機感から発奮して、上の2になる人もいます。
つまり、下の人間を排除しても、組織メンバーが変わることで、人の心理に何かしらの影響を与え、結果的に新たな262が生まれるわけです。
組織の人事を決める役職の方には、是非知っていてもらいたい法則です。
テレアポ

私のブログではテレアポのノウハウについて紹介していますが、テレアポもパレートの法則があてはまります。
テレアポで話をまともに聞いてくれる電話は10件中2件くらいの割合です。
その2割のなかで、テレアポのスキルを活用してアポイント獲得に全力を注ぎます。
残りの8割は切り捨てます。
つまり、テレアポはリストの中から2割の見込み客を仕分ける作業とも言えます。
ビジネスの世界
ビジネスの世界でも、様々な視点でパレートの法則が見られます。
・売上の8割は全顧客の2割が生み出している
・商品の売上の8割は、全商品銘柄のうちの2割で生み出している
・売上の8割は、全従業員のうちの2割で生み出している
・仕事の成果の8割は、費やした時間全体のうちの2割の時間で生み出している
私も旅行会社時代に店舗運営をしていたときに262の法則を実感した経験があります。
来店してくる顧客のデータを分析をしていたところ、以下の割合になっていたのです。
A 旅行の予約を目的に来店:2割
B 旅行を検討または相談:6割
C ただ話を聞くだけ・冷やかし:2割
こういう数字が分かれば、戦略も立てやすくなります。
例えば、誰が担当になっても成約になりそうなAのお客様には新人が担当し、担当の提案次第で成約になるBのお客様にはベテランの担当、誰が担当になっても成約にならないCのお客様には個人成績に関係のないマネージャーが対応します。
戦略はそれぞれありますが、262の法則を知っていることで、店舗運営の戦略に役立ちます。
世の中のお金
お金に関わる書籍など読んでいると、よく目にしますが、世の中のお金もパレート法則で成り立っていると言われています。
・世の中のお金の8割を2割の人で分け合っている
・世の中の富裕層は全体の2割
平成29年度の国税庁の民間給与実態統計調査のデータによると、年収200万以下は21.9%、200万超え600万以下は58.2%、600万超え以上は19.9%と、おおよそ2-6-2に分けられます。
平成29年 国税庁 民間給与実態統計調査 給与階級別給与所得者数・構成比
| 区分(男女) | 構成比 | |
| 100万以下 | 8.4% | 21.9%【2】 |
| 100万超え200万以下 | 13.5% | |
| 200万超え300万以下 | 15.8% | 58.2%【6】 |
| 300万超え400万以下 | 17.5% | |
| 400万超え500万以下 | 14.8% | |
| 500万超え600万以下 | 10.1% | |
| 600万超え700万以下 | 6.3% | 19.9%【2】 |
| 700万超え800万以下 | 4.3% | |
| 800万超え900万以下 | 2.9% | |
| 900万超え1,000万以下 | 1.9% | |
| 1,500万超え2,000万以下 | 0.7% | |
| 2,000万超え2,500万以下 | 0.2% | |
| 2,500万超え | 0.3% | |

平成29年 国税庁 民間給与実態統計調査 給与階級別給与所得者数・構成比
蟻の世界

人間界でだけでなく自然界でもこの法則があてはまるケースがあります。
有名なのは蟻の話。
働き蟻のうち、よく働く2割の蟻が8割の食料を集めています。
本当に働いている蟻は全体の8割で、残りの2割の蟻がはサボっています。
よく働いている蟻と、時々サボりながら普通に働いている蟻、ずっとサボっている蟻の割合が2:6:2になるのです。
このことから、働きアリの法則とも言われます。
小学校の掃除で、真面目に掃除している生徒が2割で、時々サボりながらもそこそこ掃除している生徒が6割、残りの2割の生徒が遊んでいたりします。
サボるのは蟻だけでなく人間でも同じですね(笑)。
262の法則は下の2と上の2は入れ替わる
262の法則は下の2と上の2が入れ替わることもあります。
私自身、会社員時代に実感した経験があります。
それは、旅行会社時代に店舗営業をしていた頃です。
毎月の私個人の売り上げが店舗で常に上位の成績の時がありました。
262の法則で言えば、上位の2でした。
しかし、その後、外営業の部署に異動してからは、成績がさっぱりで、部署の足を引っ張る存在になっていました。
それまで売り上げを作ることには自信があったので、かなりへこみました。
262の法則で言えば、下の2になっていたのです。
営業のスタンスが違うことで、今までの営業スタイルからのモデルチェンジに苦労しました。
過去の栄光にしがみついていたところもあって、素直に新しいやり方を受け入れることができなかったのです。
私のように、上の2にいても、環境が変わることで、下の2になってしまうことがあります。
もちろん、その逆もあります。
下の2にいても、環境を変えることで、上の2になることもできます。
プロ野球の世界ではトレードによって、能力が開花し、成績が上がるケースがあります。
最近ですと、日本ハムファイターズの大田泰示選手の例があります。
巨人時代は将来の4番と注目されていながらも、一軍に定着できず、シーズンの大半が2軍暮らし。
262の法則で言えば、下の2の選手でした。
しかし、トレードで日本ハムファイターズに移籍すると、持ち前のパワーでホームランを量産し始めました。
2019年のシーズンではチームのホームラン数2位、チーム打率でも3位と、262の法則で言えば、上の2の選手となったのです。
巨人に在籍した頃は、人気球団ならではの過度なプレッシャーが影響していたかもしれません。
理由は定かではありませんが、はっきりと言えるのは、環境を変えたことで、成果が変わったことです。
現在、下の2で悩んでいる方は、悲観することはありません。
人には必ず、何かしら優れた能力があります。
それは自分では気づいていないかもしれません。
環境を変えることで、日本ハムファイターズの大田泰示選手のように能力が開花し、下の2から上の2になることができるのです。
会社で満足いく結果が出ないときには、思い切って部署移動や転職をすることで、結果を変えることができるかもしれません。
下の2であれば、それ以下になることもないので、上の2の人よりも思い切った選択と決断ができるのではないでしょうか。
【まとめ】 パレートの法則と262の法則
世の中、パレートの法則、262の法則で成り立っていることがたくさんあります。
この法則を知っていることで、人生のあらゆるシーンで、決断する一助になることでしょう。
仕事の成果が出ていない時、会社の人間関係で悩んでいたりした時には、全体の数値を8-2または2-6-2に振り分けてみて、これらの法則にあてはまっているか分析してみてください。
下の2であった場合には、環境を変えることで、現状を打破することができます。
組織を運営している立場の人であれば、どんなに組織編成をしても、常に下の2が生まれることを理解しておきましょう。
人間関係や人材育成は原理原則に基づいた組織編成が必要なわけです。

