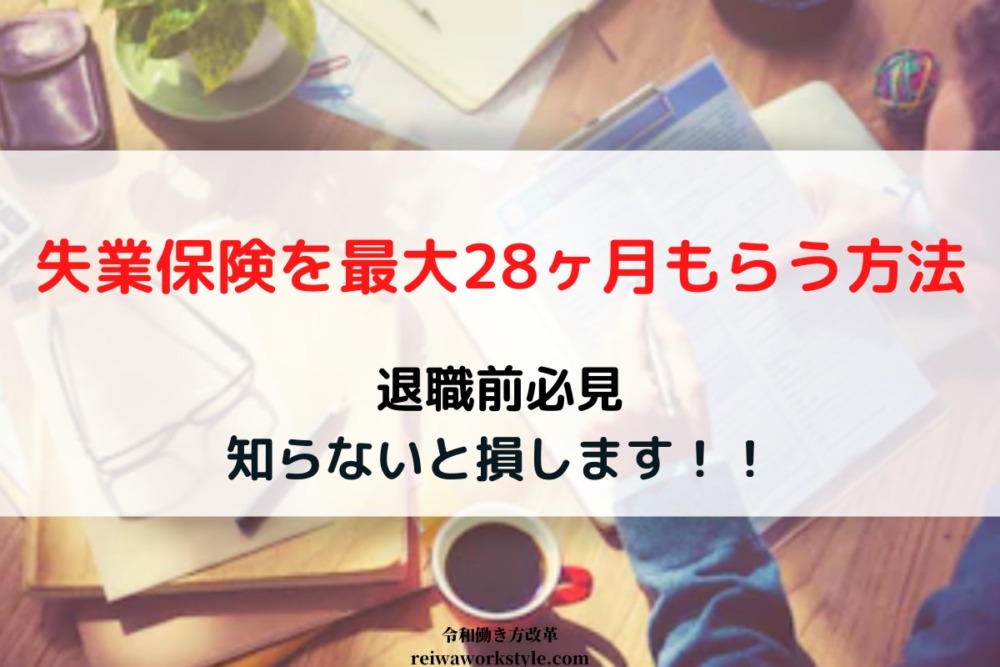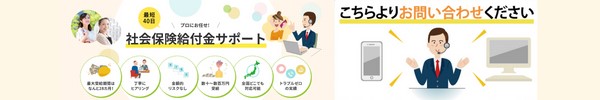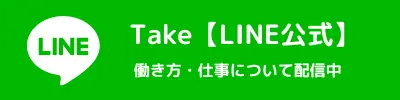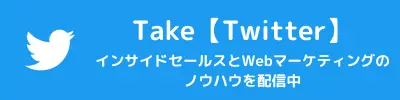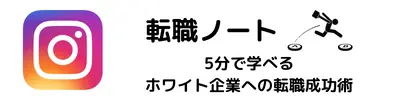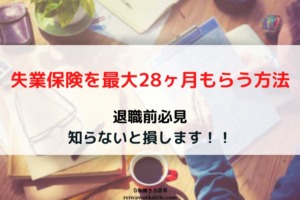会社を退職して次の仕事が決まってない場合、心配になるのはお金の不安。
次の職場が決まってから退職するのが理想ですが、そうもいかずに退職せざる得ないこともあります。
突然の倒産・解雇
休業により収入の見込みが立たなくなった
人間関係のトラブル
ストレスによる体の異変
「貯金がない」、「収入が止まる」といったお金の心配から、なかなか踏ん切りがつかない人も多くいます。
こうした状況でお金を受け取ることができるのが「失業保険」です。
会社を退職してから受け取ることができる手当として「失業保険」は広く知られていますが、最大で28ヶ月もらう方法はあまり知られていません。
本記事では、突然会社を辞めることになってしまった人に向けに、失業保険を最大28ヶ月もらう方法について解説してまいります。
こちらの記事をご覧いただければ、最大28ヶ月以上手当をもらうことができますので、お金の不安は軽減されるはずです。
実際に受け取るまでの申請の流れについてもイメージできるように紹介していますので、会社の退職が決まっている方やこれから退職を考えている方は、損をしないためにも、ぜひご覧ください。
失業保険を最大28ヶ月もらう方法とは
「失業保険は28ヶ月もらえるの?」
結論からお伝えしますと、傷病手当金受給後に失業保険をもらう合わせ技です。
傷病手当金終了後に失業保険の手続きをすることで、併給して最大28ヶ月もらうことができます。
| 健康保険の「傷病手当金」 | 最大18ヶ月 |
| 雇用保険の「失業保険」 | 最大10ヶ月(45歳以上は12ヶ月) |
| 合計 | 最大28ヶ月(45歳以上は30ヶ月) |
公的な保険である社会保険には大きく分けて4つ
・健康保険
・雇用保険
・労災保険
・厚生年金
傷病手当金
傷病手当金は健康保険に含まれます。
病気やケガで動けなくなった人の生活を保障する制度です。
・退職前12ヶ月間の給与面(額面)平均の65%もらえる
・最大18ヶ月間もらえる
30万×65%×18ヶ月間=351万円
給与が30万円の人は最大351万円もらえる
傷病手当金は病気が原因でないともらえないのでは?
傷病手当は大きい病気ではなくても、ちょっとしたメンタル面の要因があれば受給できます。
実際に、仕事を辞める時の理由として、メンタル面にリンクして使われているケースが多いようです。
・不眠症
・上司と合わない(適応障害)
・やる気が出ない(抑うつ病)
・満員電車が憂鬱
・体が重い
etc
普段であれば、病院に行く程度でない初期症状でも、申請すれば日割りでしっかりと受給できます。
ほとんどの会社員は一度くらいは経験があるのではないでしょうか?
傷病手当金については下記の記事でも詳しく解説しています。
失業保険
失業保険は雇用保険に含まれます。
就職できる状態で就職する意思がある失業者(就職困難者)に支払われる給付金です。
・退職前6ヶ月間の給付(額面)の平均60%
・最大10ヶ月間もらえる(45歳以上は12ヶ月間)
30万×60%×10ヶ月間=180万円
給与が30万円の人は最大180万円もらえる
失業保険については下記の記事でも詳しく解説しています。
つまり、給与30万円の人が傷病手当金と失業保険を最大限活用することで、最大531万円もらうことができるのです。
失業保険と傷病手当金を最大28ヶ月もらう条件
失業保険と傷病手当金をもらうには条件があります。
業務外の事由による病気や怪我の療養のための休業であること
社会保険(健康保険)に連続して1年以上加入していること(国民健康保険は不可)
病気やケガで働けないこと
連続した3日間を含んで4日以上仕事に就けず、その間の給与の支払いがないこと
虚偽の申告をしてはいけない
社会保険(健康保険)に連続して1年以上加入していること(国民健康保険は不可)
失業の状態であること(就職できる状態で就職する意思がある)
失業保険の場合、退職理由が会社都合と自己都合では受給条件は異なります。
失業保険と傷病手当金を最大28ヶ月もらう流れ
失業保険と傷病手当金は同時にもらうことはできません。
まずは、傷病手当金を受け取って、病気の治療をします。
そして、失業保険を受け取りながら、就職活動をしていきます。
STEP①:最初に傷病手当金を18ヶ月もらう
STEP②:病気が治ったら失業保険を10ヶ月もらう
もらえる期間は最大2年4ヶ月となります。
| 傷病手当金 | 最大18ヶ月間 |
| 失業保険 | 最大10ヶ月間 |
| 合計 | 最大28ヶ月間(2年4ヶ月) |
失業保険と傷病手当金を最大28ヶ月もらうために退職前にやっておくこと
在籍期間中にしなければならないことがありますので、退職の1ヶ月前には動き出す必要があります。
退職前に必ずやっておくことは以下の4つです。
STEP①:退職を打診(退職届を提出)
STEP②:在職中に連続で3日以上会社を休む
STEP③:3連休初日に病院で受診してお医者さんに働けない状態であることを証明してもらう
STEP④:退職日に欠勤する
この4つを守らなければ、もらえません。
いきなり会社を辞めずに、この4点だけは在籍中にやっておきましょう。
順番に詳しく解説してまいります。
引継ぎや上司からの説得などが想定されますので、余裕を持って2ヶ月前に打診しておくと良いでしょう。
「傷病手当金」の受け取り条件に「在籍中3日以上、傷病で働けなかった日がある」とあります。
連続3日以上とは、平日や土日祝日関わらず3連休になる場合を指します。
ゴールデンウイークなどの連休でも構いません。
有給を使っても大丈夫なので、わざわざ欠勤する必要はありません。
3連休が取れたら、連休初日に病院で受診してお医者さんに働けない状態であることを証明してもらいます。
病院は心療内科や精神科、メンタルクリニックで問題ありません。
受診は予約してから数日後だったりしますので、先に予約をしておきましょう。
病院の先生には自分の気持ちや状態を伝えます。
・会社で働くことが心身の問題で難しい
・会社を休ませてもらうための診断書を出してほしい
・診断書がないと会社が休ませてくれないと伝える
会社の現状と自分の状態をできる限り細かく伝えてください。
ここで注意点があります。
職場のストレスが原因で診断書を書いてもらうと、労災扱いとなり、傷病手当金が受け取れなくなります。
ここはお医者さんに相談するポイントですが、事情を話して原因不詳と書いてもらうのが望ましいです。
お医者さんも理解して寄り添ってくれるので、大抵のケースでは原因不詳と書いてもらえるはずです。
万が一、就労不可と認められなかった場合は、別の病院へ行ってみてください。
お医者さんも人間なので、相性やその時の相談の仕方で、判断が異なることもあります。
本当に辛いのにお医者さんが認めてくれなかった時は、病院を変えて行ってみることです。
「傷病手当金」の受け取り条件に「退職日に出勤しない」とあります。
もし、退職日にも出社していた場合、働ける人と見なされてしまい、傷病手当金を受け取れなくなってしまうからです。
荷物の整理に出社することもできませんので、最終日の前、もしくは退職日を過ぎてからとなります。
退職日が公休の場合は休んだことになるので認められます。
傷病手当金をもらうための手続き
失業保険と傷病手当金を併給してもらうには、まず最初に傷病手当金を受け取って病気の治療をします。
傷病手当金の手続きは以下の手順となります。
STEP①:健康保険を切り替える
STEP②:年金は免除申請ができる
STEP③:傷病手当金の申請準備
STEP④:2度目の通院と傷病手当金の申請書記入依頼
STEP⑤:会社に申請書の記入を依頼
STEP⑥:加入してる保険組合へ送付
STEP⑦:雇用保険の受給期間延長の申請をする
STEP⑧:その後1ヶ月に一度は通院する
順番に解説してまいります。
保険を切り替えるには2パターンあります。
A:健康保険から国民健康保険に切り替える
B:会社で入っていた健康保険を任意継続
どちらが安いかは人によりますので、気になる方は市役所(また区役所)に電話で確認してみてください。
どちらを選択しても構いませんが、必ずどちらかに切り替えてください。
退職したら国民年金は免除申請ができます。
「国民年金の退職による免除特例」がありますので、必要であれば、市役所(また区役所)に相談してみてください。
(1)申請書を入手します
申請書は在職中に加入していた健康保険組合から入手します。
多くに人が協会けんぽになりますが、その他の場合は健康保険組合連合会(けんぽれん)で調べて確認することができます。
協会けんぽの場合、ネットから申請書をダウンロードできます。
(2)申請書を記入する
申請書は記入するページが3ページあります。
・自分が記入するページ
・勤務先の会社が記入するページ
・お医者さんが記入するページ
(1)退職して1週間以内に再度病院で診察を受けに行きます。
(2)お医者さんに症状を伝えます。
・眠りが浅い
・気分が落ち込む
・集中力がない
etc
(3)申請書をお医者さんに渡す
健康保険組合から入手した申請書を渡して、傷病手当金を申請したいのでお医者さんが記入するページに記入してほしい旨を伝えます。
(4)次の診察の予約をする
1ヶ月以内を目安に次の診察の予約を取ってから帰ります。
(1)申請書を会社に送る。
健康保険組合から入手した申請書を会社に送ります。
直接渡して書いてもらうことも問題ありませんが、郵送であれば会わずに済みます。
(2)傷病手当金の申請のための記入であることを伝える
傷病手当金を申請したいので事業主記入欄に記入してほしい旨を伝えます。
(3)返送用の封筒と切手を準備する
会社側に余計な手間をかけさせないように返送用の封筒と切手はこちらで準備しておきましょう。
(4)会社からの返送を受け取る
後日会社側から返送があるはずですので申請書を受け取ります。
受け取ったら、事業主記入欄に記入してもらったかどうか確認しましょう。
書類が揃ったところで在籍していた保険組合に送付します。
申請書類を送る前に3点の記入が漏れていないか再度チェックします。
・自分が記入するページ
・勤務先の会社が記入するページ
・お医者さんが記入するページ
申請して1ヶ月くらいで、結果通知が送られてきます。
支給対象となれば「支給決定通知書」
支給対象外となれば「不支給決定通知書」
必ずどちらかが送られてきます。
次に雇用保険の受給期間延長の申請をします。
申請は退職後1~2ヶ月の間にします。
傷病手当金がもらえる条件は以下の2つのいずれかに該当したときです。
・医者が働ける状態にあると判断するまで
・申請初日から18ヶ月経過するまで
無事に治った場合、失業給付に(雇用保険)に切り替えていくのですが、失業給付(雇用保険)は退職後1年過ぎるともらえなくなります。
傷病手当金の受給期間は18ヶ月間となりますので、失業給付(雇用保険)をもらう頃には退職後1年を過ぎてしまいます。
そこで1年経っても、もらえるように受給期間延長申請をします。
(1)ハローワークへ行く
(2)受付で受給期間延長申請書を出したいことを伝えます
(3)申請理由は病気の治療のためと伝えます
退職日から32日以降でないと受け付けてもらえませんが、傷病手当金は申請等は1ヶ月はかかりますので、ここまで解説してきた手順であれば問題ないはずです。
傷病手当金がもらえるようになったら、1ヶ月に一度は通院します。
治療の意思がないと見なされないように、1ヶ月に一度、傷病手当金受給申請書を保険組合に提出します。
因みに、退職した会社に申請書を毎回書いてもらう必要はありません。
二度目以降は自分が書くところとお医者さんが書くところだけで大丈夫です。
理由は傷病手当金を申請したい期間に在職していた期間が含まれないからです。
最大で18ヶ月ではありますが、病気が治れば給付は止まります。
失業保険をもらうための手続き
次に失業保険の手続きです。
失業保険は18ヶ月間傷病手当金をもらうか、病気が治って働ける状態になったらもらうことができるお金です。
働ける状態になった人が就職活動期間中にもらうものなので、働けない人はもらうことができません。
因みに公務員の人は雇用保険がないので対象外となります。
(※傷病手当金は対象となります。)
病気の人は治って働ける状態にすることが必要です。
働ける状態であることをお医者さんに伝えて証明をもらうことができればOKです。
失業保険の手続きは以下の手順となります。
STEP①:ハローワークへ行って受給期間延長申請を解除する準備
STEP②:通っていた病院へ行く
STEP③:再度ハローワークへ行って受給期間延長申請の解除
STEP④:求職活動
STEP⑤:就職が決まった場合
順番に解説してまいります。
ハローワークへ行って受給期間延長申請を解除に必要な下記の書類を準備します。
・傷病証明書
・就労可能意見書
書類を入手したら、お医者さんに就職活動を始めることと、失業給付をもらうために必要な旨を伝えて書いてもらいます。
ハローワークへ行って働けるようになったので就職活動をしたいと伝えます。
併せて失業給付を受けたい旨も忘れずに伝えます。
その際、事前に必要な書類はこちらです。
・印鑑
・離職票
・運転免許証等の身分証明書
・マイナンバーが分かるもの
・写真(3㎝×2.5㎝ 2枚)
他にも必要な書類がないか事前に電話して確認しておくとよいでしょう。
そして、就職困難者に該当する旨を必ず伝えて下さい。
通常、失業給付は3ヶ月程度しかもらえません。
しかし、就職困難者の場合、失業給付がもらえる期間は長くなります。
| 45歳未満 | 300日 |
| 45歳以上 | 360日 |
月に一回はハローワークへ行って求職活動を行います。
求職活動期間中は失業給付を受けることができます。
健康保険の人は減免申請もできますので、必要であれば市役所(区役所)の窓口で手続します。
予め手続しておくと健康保険の負担が軽減できます。
就職が決まったら、再就職手当がもらえる可能性があります。
早くに就職が決まった場合、失業給付の給付日数が残っているので、その分を再就職手当としてもらうことができます。
給付日数の残日数に合せて、給付金を全額でもらった場合の60%程度になります。
失業保険を最大28ヶ月もらう手続きを専門家に任せる方法もある

これまで解説した内容を見ても不安、手続きが面倒、準備する時間をかけたくないと感じた方は、専門家に任せる方法もあります。
顧問社会保険労務士監修の退職コンシェルジュが運営する『社会保険給付金サポート』では、申請に面倒な手続きを全てサポートしてくれます。
仕組みを簡単にお伝えしますと、有料コンサル(合法)をしてもらい、国からもらえた金額に応じて報酬を支払うものとなります。
給付金サポートの業者を利用する際は、詐欺まがいの業者もありますので、選定に注意が必要です。
退職コンシェルジュであれば、顧問社会保険労務士監修と1200名以上のサポート実績もありますので安心して任せることができます。
退職コンシェルジュがサポートしている『社会保険給付金サポート』はこちら
国の制度を正しく知ることで失業保険を最大28ヶ月もらうことができます
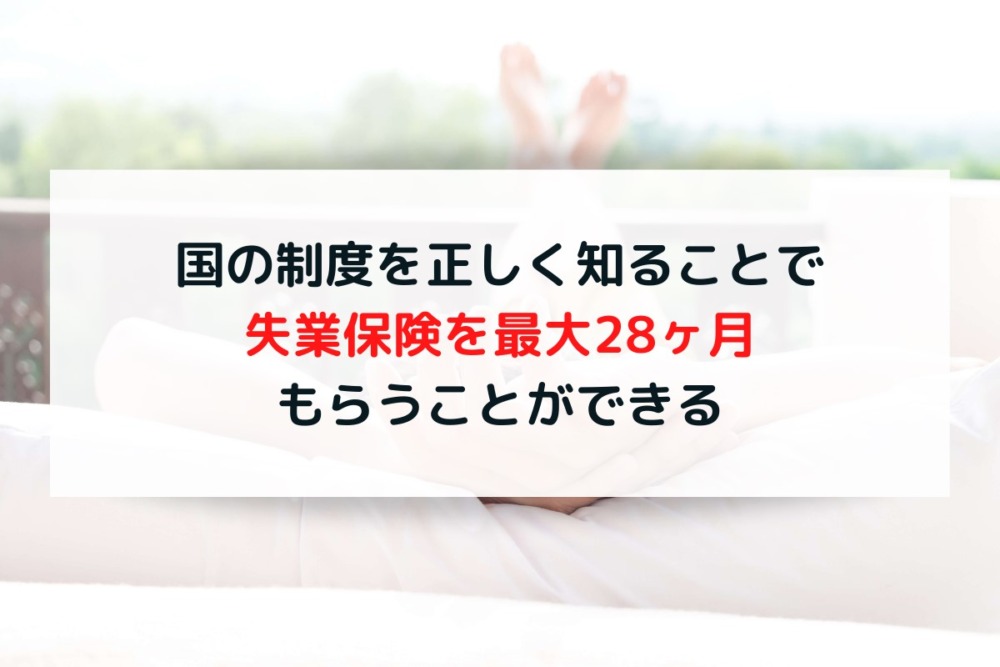
本当にこんなにもらっていいのかな?
こうしたお金をもらうことがなんとなく悪いと思う方もいるかもしれません。
失業保険と傷病手当金は国の制度によって、私たちが払ってきた保険料が原資となっています。
毎月の給料から天引きされ続けてきた保険料で賄われているのです。
つまり、私たちが国に積み立ててきたお金です。
条件にあてはまる方はもらうべき当然の権利なのです。
退職後に手当をもらえる期間が長ければ、心に余裕を持つことができます。
困窮した生活も少しは楽になりますし、治したい病気の治療にも充てられます。
次の仕事のことも慌てずにじっくりと考えることもできます。
もし、手当をもらえる期間が3ヶ月程度だとすると、次の仕事を急いで見つけないといけないですし、治したい病気も治せないかもしれません。
慌てた結果、仕事選び、職場選びに失敗してしまうなど、負の連鎖が続くこともあります。
傷病手当金と失業保険を28ヶ月もらって、のんびりしましょうということではありません。
人生の大事なリスタートであれば、腰を据えて落ち着いて考える状況にしていきましょうということです。
国の制度を正しく知ることで、失業保険と傷病手当金を最大28ヶ月もらうことができるカードを備えることができるのです。

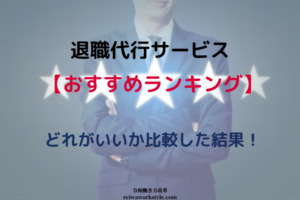
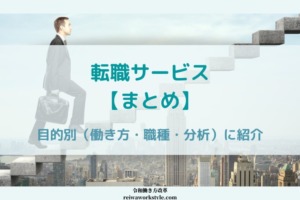
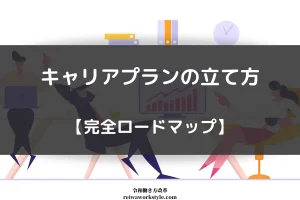
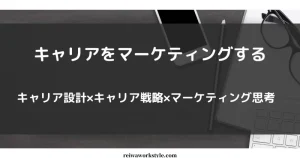
\ Follow Me! /
Sponsored Links